「スタートアップ企業の資金調達はどうすればいいの」
「スタートアップ企業は銀行からの融資は受けられないというのは本当?」
と資金調達で行き詰まりを感じている人も多いのではないでしょうか?
しかし、実際にはスタートアップ企業でも利用できる資金調達方法は存在します。
この記事では資金調達に失敗してしまう企業の特徴や、スタートアップ企業におすすめの資金調達方法、知らないと損する資金調達の投資ラウンドについて詳しく解説しています。
勢いのあるスタートアップを切るためにも、ぜひ最後までお読みください。
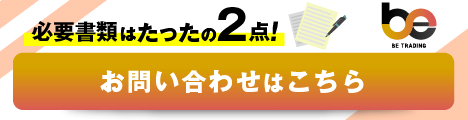
1.資金調達に失敗するスタートアップ企業の特徴

最初に資金調達に失敗してしまうスタートアップ企業の特徴を紹介していきます。
やってしまいがちな失敗を知っておくだけで今後の資金調達の動きが大きく変わっていくので、まずは一緒に確認していきましょう。
1-1.資金調達の計画が甘い
会社の経営経験値が低い場合、どうしても資金調達計画の見通しが甘くなる傾向があります。
融資などの場合は金利があるため、必要最低額を借り入れしたくなりますが、それによって十分な設備が整わなかったり、事業が進展しなかったりする可能性もあるので注意が必要です。
逆に、必要以上に融資を受けた場合、返済や金利の返済のために、資金の流れがかえって悪くなることもあります。
対策として適正な金額の資金調達を心掛けるようにしましょう。
事業を始めたばかりの頃は、研究開発費や設備などに目が行きがちですが、経営者の給与を含め、会社を維持する費用などもきちんと計算する必要があります。
十分な設備を整えるとともに、その間の生活資金なども考慮することで、事業に専念することが可能になります。
何にどのくらいの資金が必要なのか、毎月どのくらい必要なのかなど、適正な金額を出すことが大切です。
オフィスの家賃や光熱費、福利厚生費なども忘れず計算してください。
1-2.軌道に乗るまでの時間が予想以上にかかる
スタートアップ企業は経営に不慣れな場合が多いため、製品やサービスが市場に受け入れられるまで赤字が続くことがあります。
調達した資金が尽きてしまうと、その間の収入がないため生活費に困窮する場合や、新たな研究費用に投資できず、計画が頓挫してしまうことも考えられます。
経営に不安がある場合や事業に専念したい場合には、エンジェル投資家やベンチャーキャピタルからの投資を積極的に考えましょう。
ある程度のコミュニケーションが必要ですが、経済的な成功者からの助言はとても有益です。
投資家も「損」はしたくないので、積極的にアドバイスや支援をしてくれます。
また、クラウドファンディングなら市場での反応や評価がわかりやすく、事業の参考になることも多いでしょう。
1-3.一つの資金調達方法だけに頼っている
一つの資金調達方法に頼るのは危険です。
資金調達は自分の資産を売却する方法以外は、他人からの融資や投資になります。
一つの資金調達方法だけに頼ってしまうと何かしらのトラブルが発生した場合、一気に資金が消失することも考えられます。
たとえば、融資の場合は、想定以上に少ない金額しか調達ができなかったり、投資の場合は、相手との関係性の悪化で投資が中止になったりするケースもあります。
リスクを避けるためにも常に資金の調達方法は複数検討しておきましょう。
複数の方法で資金を調達できると、その分リスクも分散できるということにつながります。
より安定した経営をしていくために先に記載したやりがちな失敗は忘れないようにしてください。
2.スタートアップ企業におすすめの資金調達方法6選

早速ですがここからはスタートアップ企業におすすめの資金調達を6つ紹介いたします。
企業によって適した資金調達の方法が異なるので、全てチェックしたうえ自社に最適な資金調達方法を検討してみてください。
2-1.銀行・ノンバンクからの融資(担保がある場合)
経営者や会社に不動産などの資産がある場合、不動産を担保にしてローンなどで借り入れを行うことができます。
通常、銀行などの金融機関では融資をする際に、2期分の決算書や確定申告が必要となるため、創業の準備段階や創業間もないスタートアップ企業が融資を受けることはできません。
しかし、経営者や会社に資産がある場合は、それを担保に融資(ローン)を受けることができます。
【担保にできる資産の例】
- 不動産
- 車両
- 為替手形
- 特許権
銀行融資 ・ノンバンクからの融資 のメリットは金利が低い点です。
不動産などを担保にした場合、他の借り入れと比べて低金利で融資してもらうことができます。
金融機関は貸倒れなどのリスクが高いと金利が高くなる傾向がありますが、担保があることで信用度が増し、金利を抑えることができるのです。
たとえば一般的なビジネスローンでは金利が4%〜18%であるのに対し、不動産を担保にしたローンの金利は2.9%〜9.5%と低い水準となっています。
また借入限度額が大きいのもメリットと言えるでしょう。
担保とする資産にもよりますが、資産が大きいほど融資を受けられる金額も大きくなります。
貸倒れのリスクが低いことから、スタートアップ企業でも1億円以上の融資を受けることも可能です。
一方デメリットとしては手数料がかかる点があげられます。
不動産などを担保にする融資では、無担保の融資の場合には発生しない手数料や費用が複数かかってしまうので注意が必要です。
【必要になる費用の例】
- 不動産鑑定費用
- 抵当権、根抵当権の登記費用
- 印紙代
- その他、事務手数料など
これらを合わせると数十万円かかる場合もあり、借入総額が小さい場合はかなりの痛手となります。
また、返済不能の場合、担保を手放すことになることも忘れないでください。
毎月の返済が滞った場合、担保としていたものを手放す(処分)ことになります。
不動産については、担保とする際に「抵当権」などの登記を行っています。
そのため、金融機関が返済不可と判断した場合は、担保を売却し、売却金から融資した資金と利息を回収します。
住居している土地や建物を担保に入れている場合は、退居することになりますので注意しましょう。
2-2.地方自治体・機関からの制度融資(創業融資)
地方自治体・機関からの制度融資(創業融資)は、起業の計画段階や創業間もない企業でも利用のできる融資制度で、会社が所在している自治体で受けられます。
創業融資は、地元の起業を育て、地域の発展に貢献することが目的なので、審査が通りやすい傾向にあります。
地方自治体や機関によって、独自の創業融資を行っており、金融機関と保証協会、自治体が協力して創業間もない企業などを支えています。
ただし、会社が所在する自治体限定の場合がほとんどで、条件なども自治体によって異なります。
まずは、会社の所在する自治体の創業融資を調べてみると良いでしょう。
調べ方は、インターネットで「創業融資+都道府県・または自治体名」で検索するだけです。
自治体の創業融資を利用するメリットは先述したように審査に通過しやすい点と金利が低いという点です。
自治体の制度融資では、金利が他の金融機関と比べると格段に低くなり、借入金利の一部を自治体が負担してくれる場合もあるので、お得に融資を受けることができます。
一方デメリットは融資までに時間がかかる点で自治体の創業融資では融資までに2か月〜3か月かかるケースがあるので注意が必要です。
さらに自治体の創業融資では、自己資金が必要となるケースが多く、融資額の2分の1もの自己資金が必要となる場合があるので、覚えておきましょう。
先述したように審査に通過しやすいとはいえ、本当に事業が成立するのか、その事業内容や計画、返済予定などを説明する必要があるので事前にしっかりとした準備が必要です。
創業融資についてはこちらの記事も参考にしてみてください。
2-3.エンジェル投資家から出資を受ける
エンジェル投資家とは、事業計画の段階や創業間もない企業に対して、個人の資金を提供してくれる個人投資家で、起業の計画段階から出資を受けることができます。
エンジェル投資家は、個人の判断で数百万円から数千万円の出資を行っており、起業家にとって天使のような存在であることからこの名がついています。
エンジェル投資家が出資するには、起業家を応援したいという目的の他にも、最終的には金銭的な利益を上げるという目的があります。
まだ市場価値のないスタートアップ企業やベンチャー企業などに投資することで、その企業が急成長した場合に大きなリターンが返ってくるからです。
成長しきった企業に向けての出資よりもリスクが高い分、大きな利益を得ることが可能というわけです。
それではそんなエンジェル投資家から出資を受けるメリットから解説していきます。
エンジェル投資家から出資を受ける最大のメリットは返済義務がないという点です。
投資は融資と違い、出資で得た資金に返済義務はありません。
毎月返済することもないので、資金を事業に集中して使うことができます。
さらにエンジェル投資家の多くが経済的な成功者が多いので、経営サポートやアドバイスなどを受けることができる点も大きなメリットと言えるでしょう。
基本的に個人の資金なので、エンジェル投資家の意向によっては素早い融資も可能になります。
デメリットについても解説していきます。
エンジェル投資家は個人なので、出資規模は数百万〜数千万円程度になり出資金額が比較的少ないということを覚えておきましょう。
また、エンジェル投資家からの資金調達の場合、出資をしてもらう代わりに株式を譲渡することになります。
決議権の半分を譲渡してしまうと、最悪な場合、経営権を失う可能性もあるので注意が必要です。
2-4.ベンチャーキャピタルからの出資
ベンチャーキャピタルとは、将来有望である企業や事業に対して出資を行う機関や投資会社を指し、スタートアップ企業にも積極的に出資を行っています。
投資の目的はエンジェル投資家と同じように、起業家の支援と金銭的な利益のためですが、何人もの投資家の資金を運用しているので、エンジェル投資家よりも多くの資金を調達することも可能です。
ベンチャーキャピタルはただ出資してくれるだけではなく、さまざまな支援を行ってくれます。
たとえば、出資先の企業に対し、戦略立案から実行まで関与し、投資先の成長を促すなど経営に対してのアドバイスやコンサルを行ってくれるのです。
事業内容には精通していても、会社の経営は初めてという人にはありがたい支援といえるでしょう。
また、エンジェル投資家の投資と同様、融資と異なるため、返済義務はありません。
万が一事業が失敗しても、ベンチャーキャピタルからの返済の催促のようなものもないので、金銭的な損失は少ないといえます。
さらに先述したようにベンチャーキャピタルは投資家が集まった機関や投資会社なので、エンジェル投資家に比べて規模が大きく、億単位の高額な資金調達が可能なのも大きなメリットと言えるでしょう。
デメリットについても記載していきます。
ベンチャーキャピタルからの出資はエンジェル投資家からの時と同様に株式を出資者に保有される点に注意してください。
1株あたりの株価の価値を上げて発行部数を少なくする、最低でも株式の3分の2以上は保有しておくようにするなどの対策が必要です。
また、資金調達で事業内容が具体化されていない場合、手続きが複雑になります。
計画段階や創業間もない頃は、出資を納得させられるだけの合理的な説明や理由づけが必要です。
評価を得るには事業計画書やエクイティストーリーなどを綿密に準備し、その後面接や効果的なプレゼンテーションを行うことが求められます。
十分な準備を行い、迅速に資金調達できる環境を整えておきましょう。
2-5.クラウドファンディングからの出資
クラウドファンディングは、実現させたい事業やプロジェクトなどをインターネット上で公開し、応援したい人から資金や支援を集める方法で、スタートアップ企業向きの資金調達方法です。
クラウドファンディングは、ネットを通じて不特定多数の人からの資金提供が期待でき、2022年の時点で25をも超える媒体があります。
地域創生に特化しているものや、エンタメが中心のものなど媒体によって特徴が異なり、手数料も10%〜20%と違ってくるので、媒体の特徴や手数料などは必ず確認するようにしましょう。
クラウドファンディングのメリットは起業の計画段階や創業間もない会社でも資金調達ができる点です。
金融機関の多くは、創業から2年以上たっていることが融資条件であることが多いですが、クラウドファンディングなら計画段階から資金調達ができるため、早い段階から研究や開発費を賄うことができます。
また手続き~実際の募集まで全てインターネット上で完結するため、利用しやすい点も大きなメリットです。
ただし当然多くの人が興味を持たなかったり、支援したいと思わなかったりした場合には、資金調達ができないこともあります。
さらに申し込みをしてから実際に資金が振り込まれるまで3週間〜数か月かかる可能性やアイデアが盗まれるリスクがあることも覚えておきましょう。
クラウドファンディングでは支援を募るため、事業内容や商品・サービスを公開することになりますが、今までになかったアイデアの場合、盗用されることがあります。
それを防ぐためにも、自分のアイデアについては特許を出願しておくことが重要です。
クラウドファンディングについて詳しくは「クラウドファンディングとは?仕組みやファクタリングとの違いを解説! 」の記事をご覧ください。
2-6.ファクタリング
融資の審査を通過することや投資家からの出資を受けるのが難しいと感じている人はファクタリングを検討してみてください。
ファクタリングとは企業の売掛金をファクタリング会社に売却することで、保有している売掛金を支払期日前に現金化するサービスです。
売上はあるのに支払期日が当分先で手元に資金がない状態や、売掛先から入金がないと次の案件を受けられない状態は、ファクタリングを利用することによって解消できます。
ファクタリング会社に手数料を支払う必要はあるものの「1日でも早く資金を調達したい」という方には最適なサービスと言えるでしょう。
またファクタリングは売掛先の信用力が重要視されるため、既に銀行や投資家からの融資や出資を断れている場合でも、審査に通過する可能性があります。
現在資金繰りが上手くいってない方はファクタリングも視野に入れてみてはいかがでしょうか。
ファクタリングについては「ファクタリングとは?仕組みや注意点などを図解で簡単に解説! 」の記事で詳しく解説しています。
3.資金調達のラウンドを理解する

資金調達のラウンドとは企業の成長やサービスのリリース時期によって分けられた5つの資金調達のフェーズのことを指します。
途中で資金不足に陥るリスクを回避するためにも、資金調達ラウンドについては必ず覚えておきましょう。
それぞれのフェーズについては下記に詳しく解説していきます。
3-1.シード
シード期は起業前の準備段階の時期を指します。
ビジネスや開発する製品のアイデアのみがある状態で、サービスをリリースするために試行錯誤する段階なので赤字に陥りやすい状況です。
また、信用力も実績もほとんどないため資金調達が難しく、個人の投資家などに出資の交渉を行うことが多くなります。
このフェーズでは数百万の資金の調達を目安にしましょう。
3-2.アーリー
アーリーは起業直後のフェーズです。
サービスをリリースしていても軌道に乗っていないことが多いことに加え、会社の設立、設備の投資などコストが増えてくる段階でもあります。
シード期同様に信用、実績の面から資金繰りに苦労する段階で、個人投資家に出資を交渉しつつ公的な融資制度などの利用も検討していきましょう。
コストも増えてくることから、数千万円の資金調達を目安と考えるようにしてください。
3-3.シリーズA
シリーズAはサービスが軌道に乗り始め、事業の拡大を行っていくフェーズです。
サービスや開発した製品のブラッシュアップをしつつ、商品の拡販に向けてマーケティングやブランディング、営業などの強化も必須になります。
シリーズAのフェーズまでくると、資金の調達方法も増え始め、企業によっては金融機関からの融資も受けられる可能性が出てくるでしょう。
さらにPMF(Product Market Fit)と呼ばれる、「自社商品が市場に受け入れられている状態」が少しずつ見えてくる段階で会社の認知度も上がってきます。
資金調達の額は数千万を目安にしましょう。
3-4.シリーズB
シリーズBは先述したPMFが実現でき、競合と争いながらも売上を拡大していく段階です。
採用活動や新商品の開発も進め、事業規模を一気に拡大していくフェーズでもあります。
シリーズA同様に販促のコストや営業活動費に加え、開発費やメンテナンス費もこれまで以上に加わるため数億円の資金調達が必要です。
ただしシリーズBまで進められれば企業の信用力や実績もある程度確立されているため、資金調達の方法も増えてきます。
3-5.シリーズC
シリーズCは黒字経営が安定してきたフェーズで、IPOやM&Aといったイグジットを検討する段階にもなります。
売上が増えることで資金調達をしなくても問題ないという企業もありますが、市場やニーズの変化による売上減少のリスク等に備えて資金調達は変わらず行っていきましょう。
また企業によっては新規事業の開発や、海外への進出などさらなる事業拡大を行う必要もあるので一般的に数億円~数十億円の額の資金調達が目安となります。
4.資金調達の注意点

スタートアップ企業にとって非常に重要となる資金調達には、注意点も存在します。
金融機関からの融資の場合は審査が厳しいかつ、資金の調達までに時間がかかることがほとんどです。
健全な財務状況をアピールしたり、緻密な事業計画書の作成をしたりすることが必須となりますので事前準備を怠らないようにしてください。
法人が融資を受けるためのコツやポイントについてはこちらの記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。
またエンジェル投資家やベンチャーキャピタルからの投資の場合、譲渡する株式の割合によっては経営の自由度が下がる点に注意しましょう。
返済の義務がないというメリットがあるとはいえ、その分投資家も経営の方針を気にする傾向があるので契約前には契約内容をしっかりと確認してください。
5.資金調達で失敗しないために
資金調達で失敗しないためには、資金調達における重要なポイントを押さえておくことが大切です。
特に重要となるのは先述した資金調達ラウンド。
自社がどのフェーズにいるのかを確認しつつ、次のフェーズではどんなことをする必要があるのかを何度も見返してみてくださいね。
また、資金調達は事業計画に基づいた明確な経営戦略の基、行うことが大切です。
曖昧なまま事業をスタートさせてしまうと、適切な融資や出資を受けられず資金不足に陥ったり、資金を求めるあまり投資家に不利な条件での契約を要求されたりします。
準備の段階で緻密な計画を立てられるようにしましょう。
6.まとめ
今回は資金調達に失敗してしまうスタートアップ企業の特徴や、スタートアップ企業におすすめの資金調達方法、資金調達の投資ラウンドについて解説しました。
これから起業を考えている方や資金調達に困っているスタートアップ企業の経営者の方はぜひ参考にしてみてください。
改めて最適な資金調達方法を、最適なタイミングで行うことを心掛けましょう。
また記事内で紹介した資金調達方法のファクタリングでは売掛先の信用力が審査で重視されるため、売掛金があれば利用者の実績や信用力が低くても資金調達できる可能性があります。
またファクタリングは信用情報に影響しないため、今後融資を利用する可能性がある方にもおすすめの資金調達方法です。
ビートレーディングは取引社数7.1万社以上の実績があるファクタリング会社です。
申し込みからお振込みまでは最短2時間でオンラインで完結させることができます。
資金調達でお悩みの方はお気軽にビートレーディングまでお問い合わせください。
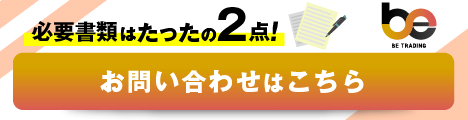

筑波大学大学院修士課程修了後、上場企業に勤務。不動産ファンドの運用・法務を担当した後、中小企業の事業再生や資金繰り支援を経験。その後弊社代表から直々の誘いを受け、株式会社ビートレーディングに入社。現在はマーケティング・法務・審査など会社の業務に幅広く携わる。
<保有資格>宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者

